三本木より


皆さんは「天皇さまは日本の象徴ってどういうこと?」という子どもたちの素朴な疑問に答えて、どう説明されますか?
天皇さまはどう思っておられるのでしょうか。私は幼い頃からずっと不思議に思っておりました。そして、なぜ「象徴」なのでしょうか。
昭和三十七年に出版された「浩宮さま」というご本を父の本棚から小学生のときに手にする機会があり、なんとなく、なるほどと思った記憶があります。
皇室の方々が、ご自身ではっきりと語られることのない内容を、美智子様の侍医であった佐藤久先生(小児科)が、謹んでお書きになったご本です。その中から、私がなるほどと思ったことを思い出しながらお話しようと思います。
私たちの心の中にある天皇さまのお姿について、きっと皆さんにも頷いていただけると思います。
ご本は、皇太子様と美智子様のご婚約の頃のお話で始まります。
先生のお知り合いのオランダ婦人が、ある時にふと、こうおっしゃったそうです。「日本の国は不思議ね。お正月以外は、国の祝日でも皇室のおめでたでも、人びとは、おめでとうとあいさつしませんね。私の国ではみなします。」

なんだかがっかりする感想を耳にされたわけですが、昭和33年、お二人のご婚約発表の日は、そうではありませんでした。この日ばかりは、日本国内、町も村も、朝から明るい笑顔の連続でした。
どの人からも申し合わせた様に、素朴な真実味のあふれることばが聞かれ、先生も、ひしひしと、新しい日本、新しい皇室を思い、胸がいっぱいになられたそうです。
皇太子さまの婚約決定についてのご希望は、「近親結婚はできるだけ避けて、家柄よりも人柄に重点をしぼられた」ように聞いておられたそうです。しかし、伝統ある皇室のご婚儀です。それは、大変なことだったと拝察されますが……。
実際に、周到な心構えの後に美智子さまとのご婚約に断然踏み切られたということについて、殿下のお近くにおられた先生方も、皇太子さまのご決断は、新しい時代の皇室の方として、さすがと、心からお喜び申し上げられたそうです。
さて、婚儀をつつがなく終えられ、順調に時は過ぎ、美智子さまがご懐妊となり、昭和35年2月23日、いよいよ浩宮さまのご誕生となりました。

ご誕生行事中もっとも重要な、おめでたい日は、民間で云うお七夜で、お名前がつく日です。
お名前は、あらかじめ二人の漢学者にご依頼され、選ばれた候補名の中から、両陛下と皇太子さまがご相談の上、一つを決められるのだそうです。これを大高檀紙(おおたかだんし)という特別の和紙に、「御名徳仁」「称号浩宮」と書き、この2枚の名記を、陛下の旨をうけた宇佐見長官から東宮太夫を経て皇太子さまへ、それから新宮さまのお枕元にという順序で伝達され、儀式を終えられます。
報ぜられたところによりますと、このお名前は漢籍の「中庸」第32章の中から選ばれたものであるそうです。この章は至誠の道を説き、その道を体得した人の姿を書いたもので、文中にある「浩々たる天」と「天徳に達するもの」からとられ、「浩浩」は大空の様に広くてかたよりのないさまをあらわし、「天徳」とは、自然の人間性「聡明聖知にして天徳に達する者」を意味するのだそうです。
「天の空の様にはるかに広く片寄らない天皇にふさわしい徳を積んでほしい」というお気持ちで選ばれたお名前だと拝察致します。
このようなご期待を担って成長された浩宮さまです。
次に、浩宮さまのご養育についてのお話でも、両殿下のお考えに深く感動を致しました。

浩宮さまがお生れになって以来、日常生活の中で先生がご覧になった数々のエピソードについてご紹介され、その出来事の中で、両殿下のご養育方針がはっきりと示されていたことをおっしゃっています。
妃殿下のお言葉には、浩宮さまへの母としての深い愛情が満ち満ちています。
「人の批判から自分を守るための外向きの厳しさや、自己満足のための厳しさを持ちたくない。私はむしろ大勢の人のさまざまな要望に、おびえてしまって、自分が徳(なる)ちゃんに子供として必要な十分な愛情をそそいであげられないことのほうが、よほどこわい。」
両殿下が、浩宮さまが大変にお小さい頃から、ご自身の力で幸福を見つける努力をされるように積極的に訓練するお考えであったことは、浩宮さまのご日常生活からもうかがえたそうです。
数々のしきたりを重んじる宮中にあって、このような、ご慈愛あふれるご両親のもと、おおらかでありながら、自己を鍛える本物のきびしさを期待される育児方針でご生育になられた浩宮さまは、誠にお幸せだと感じられたそうで、親となった現在の私も深く感銘をいたしました。
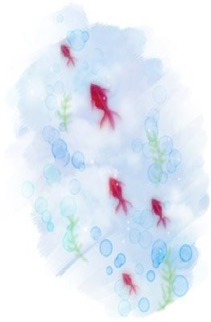
だから、浩宮さまは妃殿下がご自分でおたてになった教育方針を、素直に受け入れられたのでしょう。また、周囲の方たちも、全く妃殿下の教育方針に同調して、お世話申し上げるから、そこには何の抵抗もお感じない様にお見受けされたそうです。
教育方針と言っても、その長い針の先に、妃殿下がしっかりと焦点を絞っていらっしゃったのは、ほかならぬお父君陛下と、御夫君殿下であらせられるお二方のお人となりです。そしてそれは、妃殿下が常々考えておられた将来天皇になられる浩宮さまのお姿に他ならないのです。そのお姿とは、

私たち国民は、天皇さまのお姿を戴くことをありがたく、誇りに思い、美しい日本の国を、このお国柄を、末永く大切にして、守っていきたいと思います。

天皇さまのお姿